2週間ぶりのリハビリ!違和感の中で見つけた新たな光明!
こんにちは!「ゆるトレ部主将」のゆたゆたかです。
今回の肩の痛み治療記録は、2週間ぶりのリハビリの報告です。
今回は医師の診察はなく、理学療法士さんによるリハビリだけだったのですが、なんと担当の先生がまた初対面の先生・・・
これまでの経緯を説明する大変さや、アプローチの違いに戸惑いを感じつつも、その中で思わぬ大きな収穫を得ることができました。
それが、僕の肩の痛みの根本原因となる「左右差のある巻き肩」という指摘と、インナーマッスルに効かせるための正しいコツです。
この記事では、先生が変わったことで感じた戸惑いと、痛みを乗り越えるための新しいヒントを詳しくお伝えします。
同じように筋トレ中の怪我や肩の不調に悩む皆さんの、何かヒントになれば嬉しいです。
先生が変わったことで感じた「戸惑い」と「違和感」
今回は医師の診察はなく、理学療法士さんによるリハビリのみでしたが、ここで一つ問題が。
今回もまたこれまでの先生とは違う方が担当してくれたんです。
初対面だからこその大変さ
毎回先生が変わると、これまでの痛みの経緯や治療の背景をゼロから説明し直す必要があります。
僕の肩は注射を何回も打ったり、色々なアプローチを試したりしているので、経緯が複雑なんです。
これが正直、毎回のリハビリで一番大変なことです。
施術方針の違いに感じる違和感
そして、先生が変わると、アプローチも変わります。
これまでの先生方は、「身体の調子を整えながら可動域を広げ、痛みの原因となるフォームエラーをただす」という、僕の筋トレを応援してくれるような方向性でした。
しかし、今回の先生は「関節の位置を正しい位置に戻す」ことに重点を置いた施術で、これまでの路線とは少し違っているように感じました。
もちろん、どちらのアプローチも理にかなっているのですが、これまで継続してきた流れと違うと、ちょっとした戸惑いを感じてしまいます。
それでも、毎回新しい先生から新しい視点を学べるのは、この治療記録を続けている醍醐味でもあります。
その中で、今回得られた最大の収穫は次のセクションです。
リハビリ最大の収穫!「右肩の巻き肩」という左右差の指摘
新しい先生のアプローチに戸惑いを感じた一方で、今回のリハビリで最大の収穫がありました。
それは、自分でもなんとなくはわかっていた「左右差」という、根本的な問題の指摘です。
先生は僕の肩の姿勢を細かくチェックし、「右肩が左よりもさらに巻き肩になっている」と指摘しました。
痛みの根本は肩ではない?
これまで、僕の肩の痛みは、筋トレでの負荷や、損傷した腱そのものが原因だと思っていました。
もちろんそれもありますが、この左右差のある巻き肩こそが、痛みを長引かせている原因の一つであると再認識しました。
巻き肩が強くなると、肩関節が常に前に引っ張られた状態になります。
この状態で筋トレ、特にベンチプレスなどのプレス系種目をすると、肩の腱に不自然な負荷がかかり、炎症や痛みが再発しやすくなります。
「痛い肩を治す」ことばかりに集中していましたが、「左右の肩のバランスを整え、土台を正しい位置に戻すこと」も重要だと痛感しました。
この指摘は、今後のリハビリとトレーニングのやり方を考え直す、大きな気づきとなりました。
「効かせ方」の核心!インナーマッスルトレの真髄を学ぶ
左右差という大きな課題を指摘してもらった後、先生は僕が自宅で続けている肩関節の外旋トレーニングについてもチェックしてくれました。
僕は、教わった通りにやっているつもりだったのですが、先生からのアドバイスで、その「効かせ方」に大きな勘違いがあったことに気づきました。
強い力・速い動きはNG!
インナーマッスルを鍛える上で、僕が陥っていた間違いは「力を入れすぎる」「速く動かす」ことでした。
先生は、「強い力で引っ張ったり、スピーディに動かしたりすると、狙っているインナーマッスルではなく、アウターマッスルである三角筋に効いてしまう」と指摘してくれました。
インナーマッスル(腱板)は、小さな筋肉で、関節を安定させる役割を担っています。
ここを鍛えるには、強い力は必要なく、繊細なコントロールが求められるのです。
インナーマッスルに効かせる真のコツ
先生に改めて教えてもらったコツは、このシンプルな一点でした。
「ゆっくり、じんわりと動かすこと」
ゆっくりと抵抗を感じながら動かすことで、無駄な力が入らず、奥にあるインナーマッスルにじわじわと負荷をかけることができるそうです。
この指導は、僕のこれまでのリハビリの常識を覆すものでした。
次のセクションでは、このコツを自宅で実践した驚きの結果をお伝えします。
自宅での実践で確信!「ぼやっと疲労する」部位の正体
リハビリで教わった「ゆっくり、じんわり」動かすというインナーマッスルトレのコツ。
僕は半信半疑ながらも、すぐに自宅で試してみました。
結果は、驚くほど明確でした。
「三角筋」ではない、新しい疲労感
これまでは、インナーマッスルを鍛えているつもりでも、なんとなく肩の表面の筋肉(三角筋)に力が入り、すぐに疲れてしまっていました。
しかし、教わった通りにスピードを極限まで落とし、じんわりと抵抗を感じるように動作を続けたところ、明らかにこれまでとは違う感覚が湧いてきたのです。
それが、「肩甲骨辺りのどことも言えない部位全体がぼやっと疲労する感じ」でした。
これがインナーマッスルに効いている感覚だ!
この、ぼんやりとした奥の方の疲労感こそが、まさに理学療法士さんが言っていたインナーマッスルに効いている感覚だと確信しました。
強い筋収縮ではなく、関節を安定させるために、奥の小さな筋肉群がじわじわと使われている感覚です。
この発見は、これからのリハビリと筋トレを続ける上で、非常に大きな前進です。
今後は、この「ぼんやり効く」感覚を頼りに、インナーマッスルトレーニングの質を上げていこうと思います。
あなたの痛み、もしかして左右差が原因かも?専門家に見てもらう重要性
今回の僕のように、痛みの根本原因が「左右のバランス」や「フォーム」にあるケースは少なくありません。
日々の筋トレで頑張っていても、こうした課題を自己流で改善するのは至難の業です。
専門家に見てもらうことのメリット
- フォームの徹底改善:正しいフォームを身につけることで、故障のリスクを最小限に抑えられます。
- 適切な負荷設定:超軽量トレーニングだけでなく、回復状況に応じた最適な負荷を専門家が判断してくれます。
- リハビリトレーニング:今回の僕のように、専門的なリハビリメニューを個別に指導してもらえます。
一人で悩まず、プロの力を借りることも、長く筋トレを続けるための大切な投資です。
このブログではおススメのパーソナルジムについての記事も書いています!
\ 身体の痛みに寄り添うパーソナルジムを紹介! /
このブログでは、僕が実際に調べて厳選した、身体の悩みに特化したパーソナルジムの紹介記事も書いています。
肩の怪我明けや、不調を抱えたままトレーニングを続けている方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
パーソナルジムに興味を持ったけど、まだどのジムタイプがいいか決めかねている方は、まずこちらの記事で全体の比較をしてみてください!
まとめ:今回のリハビリで得たポジティブな収穫
今回は先生が変わるという戸惑いがありましたが、結果として、僕の治療とリハビリを大きく前進させるポジティブな収穫がたくさんありました。
今回のリハビリで得た3つの財産
今回のリハビリは、僕にとって以下のような「財産」になりました。
- 右肩の巻き肩という、具体的な左右差の課題が明確になったこと。
- 痛みの根本原因が、肩関節単体ではなく、全身のバランス、特に左右の姿勢の違いにあると確信できました。
- インナーマッスルに効かせる正しいトレーニングのコツを学べたこと。
- 「ゆっくり、じんわり」動かすことで、無駄な力を抜き、目的のインナーマッスルにアプローチできるという新しい感覚を掴めました。
- 地道な継続こそが、回復への近道だと再認識したこと。
- 派手な治療法(PRPなど)に目が行きがちですが、毎日の地道なケアの「質」を上げることが、完治への最も重要なステップです。
この新しいアプローチを継続し、次のリハビリへ繋げていきます。
肩の痛みで悩む皆さんも、焦らず、「ゆっくり、じんわり」と自分の身体と向き合ってみてください。
次回の記事も楽しみにしていただけたら嬉しいです!
【広告】トレーニングチューブをAmazon・楽天で探す
【広告】フォームローラーをAmazon・楽天で探す
👀 メニューの組み方を極めよう!!
人気シリーズ「〇〇の日を極める!」各部位のリンクはこちらから。
筋トレ初心者から上級者まで、あなたのレベルに合わせたメニューを全ての部位について紹介していますので、ぜひあなたの筋トレライフに合わせて参考にしてみてください!
🔗「胸の日を極める!」胸トレメニュー組みの解説はこちら
🔗「背中の日を極める!」背中トレメニュー組みの解説はこちら
🔗「脚の日を極める!」脚トレメニュー組みの解説はこちら
🔗「腕の日を極める!」腕トレメニュー組みの解説はこちら
🔗「肩の日を極める!」肩トレメニュー組みの解説はこちら
🔗「腹筋の日を極める!」腹筋トレメニュー組みの解説はこちら
👀 部位分けの基礎を解説!
部位分けの基礎を解説している「筋トレ分割法を極める!」シリーズはこちらから。
各部位を基礎の基礎から解説していますので、本記事と併せて参考にしててみてください!
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ胸の日の解説はこちら
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ背中の日の解説はこちら
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ肩の日の解説はこちら
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ脚の日の解説はこちら
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ腕の日の解説はこちら
🔗「筋トレ分割法を極める!」シリーズ腹筋の日の解説はこちら


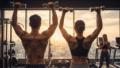

コメント